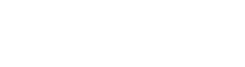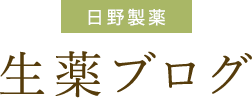薬食同次元
天然更新のキハダ

山々が萌黄色に染まり、さわやかな新緑の季節を迎えています。先月の中旬まで雪の降る日もありましたが、下旬には桜が咲きました。花びらが日の光を受けながらきらきらと舞い散る様子が美しく、心も明るく軽やかとなります。
さて、キハダの活動の季節がやってきました。今年もキハダ植樹、皮むき、実の収穫など様々なことを予定しています。
天然更新のキハダを発見
先日、弊社社員がキハダ植樹予定地の下見に行きました。カラマツなどの針葉樹が植えられていた山林ですが、所有される方がご高齢となられ、大きく育った木々を昨年伐採、撤去された後、弊社にお譲りくださいました。植樹のためには、地拵え(植栽の前に、植栽の支障となる雑草木やつる植物・伐採後の材や枝を取り除き、整理する作業)を行います。その事前確認のため、そして折角ならば生えているたらの芽を収穫しようと現地へ赴きました。すると、自然に生えたキハダが沢山見つかり、「天然更新のキハダが沢山生えていた!」と興奮して本社へ戻ってきました。
その後、その山林を一緒に見に行くと、実際に沢山の天然更新のキハダが生えていました!あちらにも、こちらにも、群生といっても良いほど、何本ものキハダが生えており、美しい萌黄色の新芽を出しています。まだ小さく細いキハダもあり、間違って踏んでしまったり、倒してしまったりしないように注意深く気をつけて歩かなくてはなりませんでした。これまで、弊社本社のキハダの近くに1、2本程度、自然に生えたキハダを見たことがありますが、このように沢山の天然更新のキハダは見たことがありません。驚き、とてもうれしく、有難く思いました。
天然更新とは?
天然更新とは何でしょうか?林野庁では「森林の伐採後、植栽を行わずに、前生稚樹や自然に落下した種子等から樹木を定着させることで、まさに天然力を活用して森林の再生(更新)を図る方法」と定義しています。自然に芽を出した樹木を大きくし、森をつくる方法を示します。「天然更新のキハダ」とは、弊社においては植樹せずに自然に芽を出したキハダのことを示しています。
なぜ天然のキハダが生育しているか?
今回天然更新のキハダが見つかった山林は、針葉樹を伐採したばかりであり、周囲は高い針葉樹で囲まれていますが、南西をむき、日当たりが良好です。また穏やかな斜面に位置しています。キハダは陽樹であり、日の光と水を好むことが知られています。一方で、弊社の経験上、あまり日当たりが良過ぎる場所も、キハダの成長には良くないようです。日中、日の光がよくあたるものの、西日については周囲の高い針葉樹でさえぎられ、水がほどよく斜面を流れると思われる今回の土地は、天然のキハダが生え易いのではないかと考えられます。また、現時点では近くにキハダの成木を見つけられていないことから、恐らく渡り鳥が村内のキハダの実を食べ、当該山林に糞を落とし、地中に種が多く存在していたのではないかと思われます。針葉樹を伐ったことで日当たりが良くなり、芽が出てきたのではないかと想像します。しかしこれらのことは仮説であり、今後専門家の方々のご意見を伺いながら、調査を行っていきたいと思います。
今回の発見に伴い得られること
国内産のキハダは年々減少しています。弊社では国内産キハダ(生薬オウバク)を用いた薬づくりを継続するために、「キハダ一本から買います」活動を実施しています。キハダを所有し、提供しても良いとお考えになる方々からキハダをお譲りいただいています。この時ご連絡いただくのは、植樹されたキハダがほとんどです。ご本人さま、ご両親さま、またはその前の世代の方々が、所有される山林や家の隣接地に苗木を植樹され、大きくなったものです。自然豊かな木曽の地においても、天然のキハダはほぼ見たことがありません。
一方、百草(ひゃくそう)は、信州木曽の伝統薬で、御嶽山を開山された修験者の方が村人に製法を伝えていただいたのが始まりとのいわれのある胃腸薬です。木曽の地に良質なキハダが多く生育していたからこそ、現代に伝わる薬であると思います。それなのに、その木曽で、なぜ天然のキハダをあまり見かけないのだろうか?どこへ行ってしまったのだろうか?と常々疑問に思い、悲しく思ってきました。
これまで様々な場所でキハダを拝見させていただいた中で、最も多く生えていたのは、北海道の中南部の天然林の中でした。1時間ほど歩く中で、20本以上のキハダを目にしました。本州ではまだこのような山林に出会ったことはありません。昔、木曽の天然林もこのような状態だったのではないか?と想像はしますが、その可能性を示唆するような密度でキハダを見かけたことはありませんでした。
しかし今回木祖村の山林内で、天然更新のキハダの稚樹を多数発見したことにより、様々な条件が合致すれば、木曽の地において、天然のキハダが多く生えることを目の当たりにすることができました。それも、偶然の1、2本ということではなく、多くのキハダの稚樹が生えていたため、少なくとも天然のキハダの発芽に適した場所であると言えます。このことは非常に大きな力と勇気を与えてくれます。今後の成長の状況によりますが、現在生えている稚樹の一部でも大きく成長した場合、キハダを含む天然林が形成されることとなります。もしかすると前述の北海道の天然林のような状態、または、もっと高い密度でキハダが生育する可能性もあります。百草が今に伝わる理由にも、近づけることになります。大変ワクワクとすることです。今後の成長をしっかりと見守っていきたいと思います。
キハダ植樹予定地を「キハダの天然林」へ
今回の山林について、キハダを植樹することは取りやめ、「キハダの天然林」として見守っていくことを決めました。人間が介在することは極力せず、自然のまま、キハダの天然林がどのように成長していくかを静かに見守り、その過程を観察、記録させていただきたいと思います。
今年はまず、周囲の草木が大きく生える前に、全てのキハダの横に目印をつけ、キハダの本数と生育場所を記録したいと思います。今後は、毎年生育状況を観察し、天然更新がどのように進むか記録していくことができればと思います。更に、近くにキハダの成木がないか、近くの針葉樹林内に前生稚樹が生育していないか等についても調査していきたいと考えています。
弊社ではこれまで将来の世代の人たちにキハダを残したいと願い、キハダ植樹を行ってきました。キハダ植樹、または、苗木を配布し他の方に植樹いただく二つの方法以外に、将来の世代にキハダを残す方法はないと考えてきました。しかし、もし、針葉樹林を伐採し、そのままとし、荒れない程度の整備をしていくことが、キハダの生育につながるのであれば、第三の方法が新たに出てきたことになります。第三の方法は、まさに、天然の森、土、水の力をそのまま活かし、森林が自ら再生する方法となります。大変夢があり、うれしく、有難いことです。
今回、キハダ植樹を予定していた山林にて、植樹など必要としない、自然の大きな力を感じさせていただくこととなりました。木が成長し、実をつけ、鳥がその実を食べ、種を運び、土に落ちた種が、日の光や水の力を受け、蓄えていたエネルギーを発揮し芽を出し、成長し、また大きな森をつくる、という自然の循環の素晴らしさを思い、人間のできることの小ささを改めて感じます。
私どもは、キハダのみならず、キハダと様々な樹種を含む美しい混交林の森を未来の世代に残したいと願っています。このことにつながる大きな学びをいただいたような気持ちです。このような学びをいただく自然の恵みに感謝し、一歩一歩、進んでまいりたいと思います。
日野製薬株式会社
代表取締役社長 石黒和佳子
出典:
島根県中山間地域研究センター「簡易地拵えの手引き」
林野庁「国有林野事業における天然力を活用した施業実行マニュアル」