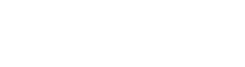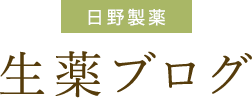薬草の花
チョウセンゴミシ(朝鮮五味子)【5月】

※チョウセンゴミシの花期は6月~7月です。
五つの味を持つ果実
(写真①:初夏、つる性の小枝に淡黄色の上品な花をつける)
秋に山里で、ブドウの房状で大きさや成熟度が異なった赤い実をつける「つる」性の樹木である。チョウセンゴミシは名前から帰化植物のように聞こえるが、本州以北に自生し、中信、東信でよく見かける。日の差し込む環境を好むため林道沿いなどの藪の中で、明るい紅色の液果をつけた姿はよく目立つ。 一方、初夏に葉裏にひっそり咲く花は、控え目で見過ごしてしまいがちである。しかし、花には芳香があり、淡黄白色の花被片は小さいが上品である。
秋に完熟した果実を乾燥させたものが「五味子」(ごみし)で、その名の由来は、皮と肉が甘く酸く、核が辛く苦く、全体に鹹(しおから)味がある、あるいはよい香りがするからだといわれる。
マツブサ科とは聞きなれない科だが、マツブサ属のチョウセンゴミシの乾燥果実を北五味子というのに対し、同じく赤い実をつけるサネカズラ属サネカズラの乾燥果実は南五味子と呼ばれる。さらに、黒藍色の果実をつけるマツブサは茎を細かく刻んで浴湯料として利用される。

(写真②:秋、紅色の液果を房状にまとめてつける)
五味子の果実には、有機酸のクエン酸、リンゴ酸、リグナン類のシザンドリン、ゴミシンなど、 セスキテルペノイドのシトラールなどが含まれる。薬効はまず鎮咳作用で喘息や 慢性の咳に用いられる。慢性下痢や発汗過多に対して収渋作用を持ち、さらに病後の衰弱者に対し滋養作用を有する。成分からは他に鎮痛、鎮痙、抗潰瘍作用が期待され、最近はゴミシンAの肝機能改善作用が注目されている。
Schisandra chinensis マツブサ科マツブサ属
生薬名●五味子(ごみし)
【ミニ図鑑】古く朝鮮から渡来したともいわれる。長野県内では標高千㍍ほどの高原におもに見られる。
▶花期 6月~7月

(写真③:同科サネカズラ属の常緑つる性木本・サネカズラの実)
出典:「信州・薬草の花」(クリエイティブセンター)
市川董一郎(文)栗田貞多男(写真)