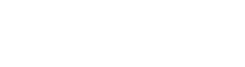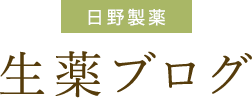薬草の花
マタタビ(木天蓼)【10月】

※マタタビの花期は6月~7月です。
遠くから虫を呼ぶ真っ白な葉
(写真①:花は葉の下に咲き目立たないが、開花期に合わせて枝先の葉の一部が白くなる)
マタタビはつる性の樹木で、六~七月ころ、緑深い山中で真っ白い葉をたくさんつけている姿をよく目にする。長野県内の山地に広く分布するが、初夏の開花期に合わせて枝先の葉の葉緑素が抜け白くなるという変わった性質がある。花は直径二センチほどの白い五弁花で、葉のわきに下向きに咲く。梅雨の時期に雨に濡れることなく受粉率を高めるために花は葉の下で咲く。しかし、それでは雨はしのげるか、虫たちの目には留まりにくい。それを補うため、葉か白化して遠くから虫たちの目に留まりやすくし、さらに、花は芳香を漂わせハチやチョウを呼ぶ。
果実は長さ三センチほどの長楕円形だが、花の子房にマタタビアブラムシが産卵すると、果実はでこぼこな虫こぶに成長する。それを干したものは、生薬名「木天蓼」(もくてんりょう)と呼ばれ、冷え性、神経痛、むくみなどに民間で利用される。成分はトリテルペノイドのほかに、ある種のアルカロイドなどである。木天蓼には強壮作用はなく、疲れきった旅人がマタタビの実を食べて「また旅」に出たという説は疑わしい。 マタタビの語源はアイヌ語のマタタンプ(冬、亀の甲) であるという。

(写真②:長さ3㎝ほどの実。薬用には虫こぶのついた実(左)を使う)
下水内地方の土産店ではマタタビの塩漬けが売られている。食べてみたが、言われるほど元気が出た気もしなかった。むしろ、果実や葉や茎に含まれるマタタビラクトンは、ネコ科の動物を興奮させ、陶酔状態にする。 マタタビか効くのはヒトよりネコのようだ。 マタタビ科マタタビ属の植物にはサルナシや家庭でもよく栽培されるキウイフルーツがあり、あらゆる部位をネコが好む。
Actinidia polygama マタタビ科マタタビ属
別名●ワタタビ 生薬名●木天蓼(もくてんりょう)
【ミニ図鑑】 マタタビ属の花は白の五弁花でいずれも美しい。
▶花期 6~7月

(写真③:同属のキウイフルーツの雄花)
出典:「信州・薬草の花」(クリエイティブセンター)
市川董一郎(文)栗田貞多男(写真)