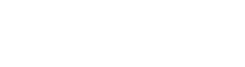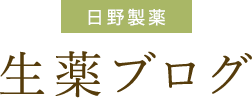薬草の花
トクサ(砥草)【8月】

※トクサの花期は7月~8月です。
眼疾の治療や下痢止めにも
(写真①:夏、茎の先端にツクシのような胞子のう穂を載せる)
あまりなじみのない植物だが、スギナの仲間である。茎はところどころに節があり、その先端に茶褐色の花(胞子のう穂(すい))がつく。簡単にいえば、スギナの頭にツクシを載せたような姿がトクサである。シダ植物でトクサ科に属し、県内でも山地の水辺や日陰に群生している。私はどちらかというと中南部の山間地でよく見かけた。茎全体が濃い緑色で、他の植物とは明らかに姿、形が異なるため目立ちやすい。背丈が高くすらりとしたその姿から、栽培もされ生け花の花材にもよく使われる。
トクサの茎は硬質だが、それはケイ酸を多く含むためである。茎をゆでて乾燥させれば、ざらざらした触感の素材が得られる。昔の人はトクサを今の紙やすりのように使い、これで建具や細工物を研磨した。つまり、「砥ぐ(とぐ)草」、これがトクサの名の由来である。
生薬名は「木賊(もくぞく)」で、成分に硫黄化合物のジメチルスルフォン、アルカロイドのパロストリン、他に脂肪酸エステルを含む。漢方ではおもに結膜炎などの眼疾の治療に、煎じ液で洗浄したり服用したりする。民間薬としては、下痢止めや止血薬として用いられた。ただし、 同じ仲間のイヌトクサによる牛馬の中毒が報告されており、薬草としての服用は注意が必要である。

(写真②:高さは30~100センチほど。直立し群生する)
トクサ科のスギナはありふれたシダ植物で、春先に胞子茎 (ツクシ)の先端に胞子のう穂がつき、続いて緑の栄養茎が伸びてくる。トクサ科の胞子は葉緑素をもつため緑色で、四本の手のような弾糸(だんし)を持つ。その形はユーモラスで、字宙人のようにも見え神秘的でもある。身近に顕微鏡があったら、スライドガラスの上に、胞子を落として観察してみてほしい。
Equisetum hyemale トクサ科トクサ属
別名●ツメトギ、ヤスリグサ 生薬名●木属(モクゾク)
【ミニ図鑑】トクサの祖先は中世代(約二億五千万~六千五百万年前)に栄え、石炭の原料になった。
▶花期7月~8月

(写真③:春一番に良く見られるスギナ。ツクシはその胞子茎)
出典:「信州・薬草の花」(クリエイティブセンター)
市川董一郎(文)栗田貞多男(写真)