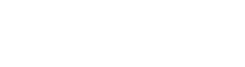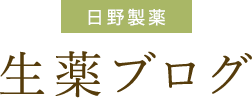薬草の花
クチナシ(山梔子)【3月】

※クチナシの花期は6月~7月です。
料理の色付けや染料にも。
(写真①:初夏、大型の白い6弁花を咲かせ甘い芳香が漂う。花はやがて黄変する。)
歌謡曲の「くちなしの花」を聴くと哀愁を感じるが、実際に花を見ればその華やかさに驚く。純白でおおらかな花は気品があり、そのうえ花が発する芳香がなんともかぐわしくあたりに漂う。写真は一重咲きだが、八重咲きの園芸種もあり、さらに花姿は豪華である。
クチナシの実は晩秋に完熟し、その赤黄色の色調と独特の形はよく目立つ。乾燥させた実は、キントンや沢庵(たくあん)漬を始めとする日本料理の黄色い色付けや、染料などに使われる。無毒の自然食として、最近になってまた注目されるようになった。
生薬名は「山梔子」(さんしし)で、よく熟した果実を陰干ししたものである。消炎、解熱、止血、鎮静作用を持ち、漢方では内服して黄疸、血便、血尿、不安、不眠に用いられる。さらに民間では外用薬として、打ち身、捻挫、痔疾に使われる。成分は、イリドイド配糖体のゲニポシド、カロテノイド系黄色色素のクロシンなどである。
(写真②:螺旋状に渦を巻いたような蕾)

クチナシは果実が熟しても開かないことからの 「ロ無し」と名付けられたとされるが、裂開する果実とすればザクロぐらいで、むしろ割れない果実の方がずっと多いのでこの説は没。 一方、クチナシは昔は「朽縄梨(くちなわなし)」と呼ばれたことは確かである。「朽縄はヘビの古名であり、果実は食料にはならず、ヘビくらいしか食べないから」との説明があるが、 これも釈然としない。私は、クチナシの蕾の、螺旋状に渦を巻いたような形を朽ちた縄 (あるいはヘビ)に見立てたと考えている。
Gardenia jasminoides アカネ科クチナシ属 別名●センプク 生薬名●山梔子(さんしし)
【ミニ図鑑】クチナシは暖地では自生するが、最近の気候では長野県でも露地で越冬する。
▶花期 6月~7月

(写真③:秋、完熟した実を採り陰干しする)
出典:「信州・薬草の花」(クリエイティブセンター)
市川董一郎(文)栗田貞多男(写真)