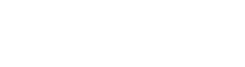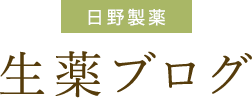薬草の花
ウツボグサ(靫草)【11月】

※ウツボグサの花期は5月~7月。
夏に枯れる花穂、生薬名の由来
(写真①:夏の到来を告げるあでやかな花色)
ウツボグサは里山や少し標高の高い日当たりのよい草原、さらに通行量の少ない林道の脇などに生しているのをよく見かける。夏の到来を告げるかのようにあでやかに咲く、その花色が印象的である。花茎の先端を多数の萼が取り囲み、赤紫色の唇状花が下から上に向かって輪状に咲く。花穂の上部にはこれから咲く花が控えており、花は長期間にわたって咲き続ける。また、高山では同属のタテヤマウツボグサが夏山シーズンに開花する。より赤紫色が濃く、たくましさを感じさせる。 盛夏には花穂全体が茶色に枯れ、これが生薬名の「夏枯草」の由来である。先端部の花が咲き終わるころに花穂を摘み取り乾燥させ、それを煎じて服用する。成分は多量に含まれる塩化カリウム、トリテルペノイドのウルソール酸やその配糖体のプルネリンなどで、利尿消炎の作用が知られている。
漢方薬や日本の民間薬として広く利用されてきた。

(写真②:真夏には花穂が枯れ、「夏枯草」とよばれる)
ウツボグサの名は、靫の形になぞらえてつけられた。靫は矢を入れ腰に着けて持ち歩く筒型の容器で、弓矢合戦が中心の鎌倉室町期の武士がよく用いたものである。長い竹龍で作ってあり、外側を動物の毛皮や鳥の羽で覆ってあった。ウツボグサの花をよく見れば、鳥の羽を纏った靫に似ていなくはないが、むしろ、食虫植物のウツボカズラの方がその形をよく表しているように思える。一方、魚の「ウツボ」はその形態から、さらに、靫という地名が下伊那郡平谷村にあるが、そこの地形が靫を連想させるのであろう。
Prunella vulgaris subsp. asiatica シソ科ウツボグサ属
別名●カゴソウ、ナツガレソウ 生薬名●夏枯草(かごそう)
【ミニ図鑑】 唇状花を抜き取り、基部を吸うとほんのり甘い
▶花期 6~8月

(写真③:同属のタテヤマウツボグサ。高原や高山にみられる)
出典:「信州・薬草の花」(クリエイティブセンター)
市川董一郎(文)栗田貞多男(写真)