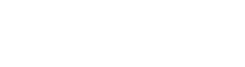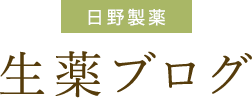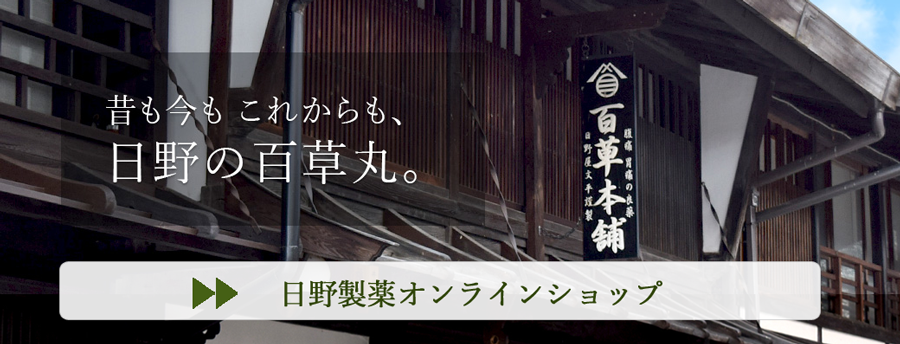生薬の話
色と薬のつながりについて

キハダの皮むきの季節が訪れています。ミカン科の落葉高木キハダの周皮を除いた樹皮である生薬オウバクは、百草・百草丸の主原料です。キハダの木を伐り、寝かせ、外側の皮をむくと、大変鮮明な黄色の樹皮が内側に現れます。その光輝くような、鮮やかな黄色には毎年、毎回驚きを覚えます。その何ともいえない美しい光は、キハダの命の輝きそのもののようで、それをいただいて薬づくりをすることへの大きな責務、そして感謝の気持ちを覚えます。その黄色の樹皮には薬効成分があり、古くから生薬として用いられてきました。また黄色の染料としても使われてきました。
色と薬には深いつながりがあります。染料として用いられる植物などの天然原料は、生薬として用いられるものが多くあります。例えば、藍は青、紅花は赤、黄柏(キハダ)は黄、紫根は紫、と美しい色をもたらしますが、一方で薬用にも用いられてきました。
■薬と色
●蓼藍
<薬用として>
薬用部位:①種子,②葉
生薬名:①藍実(ランジツ)、②藍葉 (ランヨウ)
作用:①消炎,解熱,止血など。扁桃腺炎,咽頭炎などに服用
②虫刺され,痔など
<染料として>
部位:葉
色:藍色
●紅花
<薬用として>
薬用部位:花
生薬名:紅花(コウカ) ※日本薬局方収載
作用: 駆瘀血(血の滞りを治す)、鎮痛など。産後の不調,更年期障害など婦人科系疾患広く用いる。
<染料として>
部位:花
色:赤
※種子から取れるベニバナ油は食用油として使用
●黄柏
<薬用として>
薬用部位:周皮を除いた樹皮
生薬名:黄柏(オウバク) ※日本薬局方収載
作用: 苦味健胃、整腸、消炎,収斂、清熱
<染料として>
部位:周皮を除いた樹皮
色:黄
●紫根
<薬用として>
薬用部位:根
生薬名:紫根(シコン)※日本薬局方収載
作用:創傷治癒促進、血行促進、皮膚機能の回復
<染料として>
部位:根
色:紫
「薬を服用する」と言いますが、この「服」は、衣服を現しており、身体にまとうことで病を防ぐことを古くは「外服」、身体の中に取り入れて病を予防・改善することを「内服」と言ったそうです。
■五行について
五行思想とは、古代中国の自然哲学に基づく思想で、自然界の万物は「木、火、土、金、水」の5つの要素に分類され、それらが相互に作用することで自然界のバランスが保たれるとの考え方です。医学、天文学、占いなど様々な分野で活用されてきました。
五行に基づき、五色として「青(緑)、赤、黄、白、黒(紫)」が定義されています。青、赤、黄は三原色であり、これと白、黒があれば自然界の全ての色を現すことができます。また、人体の働きを5つに分類したものが五臓です。五臓は「肝、心、脾、肺、腎」であり、臓器より広い概念的な機能を示しています。
五行の土は、五色では黄、五臓では脾にあたります。脾とは消化吸収を通してエネルギーを補充する機能で、胃腸などの消化管や膵臓と関係しています。不思議なのは、消化吸収作用に働きかける天然の生薬は、黄色をしているものが多いということです。キハダの樹皮であるオウバクは勿論のこと、黄芩(オウゴン)、黄連(オウレン)、大黄(ダイオウ)、山梔子(サンシシ)、ウコンなどは黄色をしています。
また、五行の火は、五色では赤、五臓では心にあたり、血を巡らせ、身体の働き全体を司る機能を示します。血を巡らせる生薬にも、赤い色のものが多いです。紅花は、上記の通り、血の滞りを促します。また茜の根である茜草根も、生で用いると血の流れを促します。
■最後に
天然原料による色と薬は表裏一体であり、同根であると思います。これらをうまく用いて健やかな暮らしを育んだ先人の知恵は素晴らしいと思います。美しいものを美しいと感じ、自らの身体の不調に心を傾け手当する心は、同じ源から来ているように感じます。自然の恵みに感謝し、薬も色も未来へ継承していくため、研鑽して参りたいと思います。