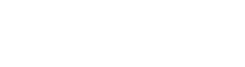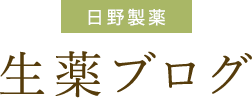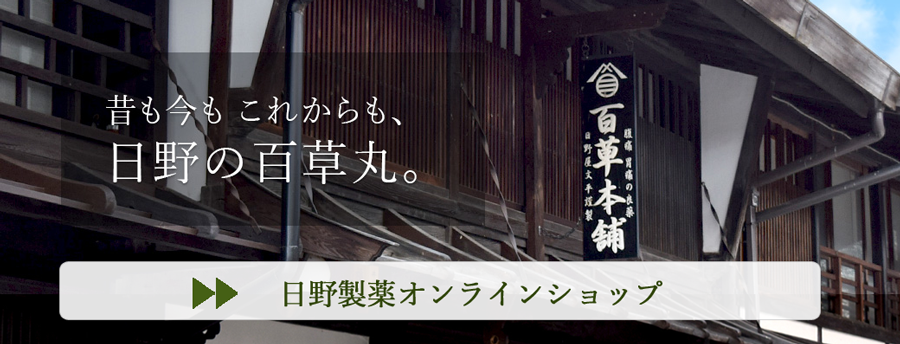生薬の話
香りについて学ぶ

福寿草が咲き、春らしい暖かな日が訪れるようになりました。本社の雪もようやく溶け、山から鳥や動物の鳴き声が聞こえ、生き物が動き出す気配を感じています。4月から新たな生活・仕事・学校を始められる方々もいらっしゃると思います。どうぞ新たな一歩を健やかに踏み出されますようにお祈りしています。
さて、弊社ではキハダを用いたお香の開発を行っています。ミカン科の落葉高木であるキハダは、特にその実に柑橘類の爽やかな香りがします。キハダの木を、皮むきの適時である梅雨の頃に伐倒すると、青い実がついていることがあります。生り始めの美しい青々とした実に申し訳なく、何かをすることができないかと、しばらく前から考えていました。少量しか採取することのできない実から香り成分を取り出し、より多くの方に良い香りをお感じいただくため、お香に練り込むことを考えました。この夏には皆様の元へお届けさせていただきたいと考えています。
お香の開発にあたり、素晴らしいお香製造会社さまとの出会いがありました。天然の香りの良さをそのまま活かしたお香づくりに専心され、より良い原料、製法を常に追求されています。打ち合わせのたびに新たな学びをいただきます。「香りを通して人を喜ばせたい」との信念のもと、お香づくりの考え方、様々な原料、調合方法、歴史や使い方を教えていただきますが、いつも新たな驚きがあり感銘を受けます。
お香の歴史
さて、お香とはいつから日本にあり、どのようなものでしょうか?
お香は、飛鳥時代の仏教伝来の頃、様々な仏教儀式とともに、大陸から日本に伝えられたとされています。
日本で最も古いお香の記録は「日本書紀」にあります。595年(推古三年)淡路島に漂流した流木を、島人が薪として火にくべたところ、素晴らしい香りが遠くまで広がったため、朝廷へ献上したとの記述があります。聖徳太子はこの流木を「沈香木」であると教えたそうです。
奈良時代に、鑑真和上が来日され、仏教の戒律とともに、医学、薬草、建築、美術、そしてお香の調香技術も伝えられました。鑑真和上がもたらされた香料には、沈香、甘松香、麝香などが含まれるそうです。お香はそれまで、主に仏前を清め邪気を払う「供香(きょうこう・そなえこう)」として用いられていましたが、調香技術がもたらされたことにより、貴族が日常生活の中でも香りを楽しむようになりました。
平安時代には、香料を複雑に練り合わせ、炭火でたく「薫物(たきもの)」「空薫物(そらたきもの)」が貴族の間で広がりました。自ら調合した薫物をたきしめ、部屋、衣装や和紙などへ移し、香りを楽しむようになりました。また、鎌倉時代には武士の台頭に伴い、禅宗が広がり、香木一本と向き合い極める「聞香(ききこう・もんこう)」が確立されました。これが後の香道にもつながります。江戸時代以降は、貴族、武士のみならず、経済力を持つ町人にも香りの文化が広がりました。
現代においても、香木、香料は、暮らしの中で使われています。香木とは、材そのものに芳香を有する木で、伽羅(キャラ)、沈香(ジンコウ)、白檀(ビャクダン)などがあります。また、天然の香料には、桂皮(ケイヒ)、大茴香(ダイウイキョウ)、丁子(チョウジ)、安息香(アンソクコウ)、龍脳(リュウノウ)、山菜(サンナ)など様々な種類があります。
香りと人の身体
香りは、ストレスや疲労感を軽減し、心身をリラックス、リフレッシュさせることが経験的に知られています。嗅覚は、脳の中でも感情、直観、本能的な行動に関わる大脳辺縁系に直接つながっています。また香りは脳の視床下部に伝わり、自律神経、ホルモンの内分泌や免疫の働きにも影響を及ぼすとされています。
香りが人の生理・心理に与える影響はまだ未解明のことも多く、着香および味を付与することを目的として使用される香料について、効能・効果を標ぼうすることはできません。
しかし近年、香りは脳の働きを刺激またはリラックスさせ、記憶力・集中力の向上や、認知症の予防、免疫力の向上にもつながるとの研究も進められています。更に、アロマセラピーが補完医療として医療や介護の現場で活用されるようになっています。
生薬と香り
生薬は香り豊かなものが多いです。生薬とは天然から得られる動植物の薬用とする部分、細胞内容物、分泌物、抽出物又は鉱物などを示します。
弊社の普導丸(ふどうがん)は、めまいや気分不快などの不調を予防し、7種類の天然の生薬として、オウバク、ケイヒ、ショウキョウ、ガジュツ、センキュウ、トウキ、ウイキョウの粉末を配合しています。いずれも香り高い生薬です。
例えばケイヒは、クスノキ科のケイヒの樹皮又は周皮の一部を除いたもので、古くから胃腸の不調に用いられてきました。ケイヒの甘くスパイシーな香りは、香料としてはもちろん、香辛料のシナモンとして愛用されています。また、ガジュツも胃腸の不調に用いられる生薬ですが、弊社では品質の規格試験において、ガジュツから抽出される精油の量を測定しています。
普導丸は、その香りを好まれるお客様も多くいらっしゃいます。生薬学の専門の先生より、普導丸が不快感を軽減するのは、服用後、胃の中から芳香が立ち上ることも影響しているかもしれない、とのお話をいただいたこともあります。普導丸の香りが、皆様の健やかな暮らしの一部となっていましたら、大変うれしいことです。
最後に
香りの世界は奥深く、学ぶことが沢山あります。しかしお香製造会社さまとの出会いを通し、改めて香りに魅了されています。心地の良い香りを有する天然のものがあり、私たちの暮らしを和ませてくれることは、大変貴重で有難いことと思います。一方、昨今は、自然環境や社会の変化に伴い、沈香や白檀などの香木は入手が困難になっているとお聞きしました。このことは、キハダの現状と似ているように感じます。
薬、食、香はつながっていることを感じます。自然の恵みを用いて健やかに暮らす先人の知恵を未来につなぐため、また多くの方々に喜んでいただくため、分野は違えども、ともに切磋琢磨し歩むことができたらと願っています。
出典:
香老舗松栄堂様HP
薫寿堂様HP
日本食生活学会誌 Vol.21 No.3 (2010)「香りの分析と香りの効能効果について」
高柳深雪氏「人間の心と身体に与える香りの効果」